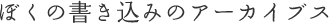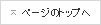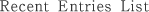2006-10-08 01:35:31
仕事とは、職務とは

▼わたしたちの、かけがえのない祖国に新しい政権が生まれてから、きょう(10月7日土曜)で2週間近くが過ぎた。
そのあいだ、ほとんどまともに首都にいなかった。死のロードだなぁ、これはと、思わず呟くような出張の日々が続いている。
その2週のあいだ、新政権を支えるひとびとから、新政権と鋭く対立するひとびとまでと、電話と電子メールを使ってやりとりをしながら、正直、ぼくは憂いをいだいた。
とくに10月5日木曜に衆院予算委員会が始まってから、憂いは急速に、深まった。
きのう金曜日の朝、羽田から関西国際空港へ飛ぶ飛行機に乗るとき、搭乗口近くのテレビで田中真紀子代議士と安倍晋三首相が、たがいに額に青筋を立てるように質疑に臨んでいるのを、ほんの一瞬だけ見た。
夜、東京に戻って、質疑のフルテキストを取り寄せた。
この質疑に、嫌なものを感じた国民は多いのではないだろうか。真紀子さんの拉致をめぐる質問は、おそらくは拉致被害者の家族の胸にも響かない。
ぼくは被害者のひとり、有本恵子ちゃんと幼稚園が同じということもあり、有本さんご夫妻の永い苦闘を目の当たりにしてきた。
それは、ごくまっとうに生きてきた庶民を、北朝鮮というテロ国家が突如、理由もなく死よりも苦しい痛みのさなかへ突き落とすという、世界にも類例のない、許されざる悲劇だ。
だが同時に、有本さんご夫妻や横田さんご夫妻の「わたしたちの娘だけが帰ればいいのではない。みなを、最後のひとりまでを取り戻すことだけが、わたしたちの闘いです」という生き方に、ぼくら日本国民はずいぶんと教えられ、勇気づけられてもいる。
拉致被害者の家族会のかたがたの生き方は、「私(し)に発して公(こう)に至る」という、戦後の日本としてはまったく新しい生き方だと、ぼくは考えている。
真紀子さんの政略的にして品を欠く質問は、その家族会を支え、後押しするのではなく、むしろ家族会が生み出した尊い価値観を、傷つけるにちかいものだったのではないかと思う。
▼しかし真紀子さんは今や、ただのトリックスターだ。
田中真紀子さんが外相だったときの狂態を、冷静に今も覚えている国民は少なくない。
安倍政権初の衆院予算委での最大の問題は、安倍首相と真紀子さんとの質疑にあるのではなく、菅直人さん、岡田克也さんとの質疑にあると思う。
ぼくが関西テレビの報道番組「ANCHOR」で安倍外交について話した翌日の、10月5日と6日に、その質疑はおこなわれた。
先に述べたように、拉致被害者の家族会が明示する生き方は、わたしたちの日本国が戦争に敗れてから喪っていたものを取り戻す生き方ではないだろうか。
発したところは、あくまでも「わたしの肉親を返して」という、たいせつな、たいせつな私的な思いだ。
そして、そこにとどまらず、おなじ被害にあったひとびとの最後のひとりまでを取り戻すために闘ってこそ、わたしたちは人間であり、おなじ同胞(はらから)の最後のひとりまでを取り戻すまで闘ってこそ、この日本は国民国家だという、公(おおやけ)を掲げる生き方に至っている。
ぼくは、これこそ「ほんものの日本型民主主義」の芽生えだと考えている。
安倍政権は、その芽生えを育てるためにこそ、誕生したのではないのか。
菅さんと岡田さんの質問は、戦争責任をめぐる諸問題を追及しているようでいて、そうではない。
中国をはじめとする外国の視点で、自国の宰相の足元をすくおうとしたと言わざるをえない。「中国や韓国が支持してくれているんだから、とカサにかかって質問しているような嫌な感じがしたね」とぼくに電話で語った、経済界の友人もいる。
日本国は、1952年4月28日にサンフランシスコ講和条約が発効したとき、主権国家としての独立を回復した(ただし沖縄諸島、尖閣諸島など南西諸島は1972年の日本返還まで独立の回復が遅れた)。
極東国際軍事裁判(東京裁判)の効力は、そこで消滅した。
なぜなら独立国家の責任とは、わたしたち主権者がみずからの視点で、みずから明らかにするものであり、独立を回復した以上は、東京裁判のように二度と外国から裁かれるゆえんはない。
日本の視点で申しているのではない。国際社会の真ん中、すなわち国際法の視点である。
ところが菅さんと岡田さんの質問は、公平にみて、東京裁判に依拠し、中国や韓国の視点を重視していた。
すなわち、それら質問は、戦争責任をめぐる追及ではなく、安倍新首相の変節や曖昧さを追及する政略であった。
そして、その安倍新首相の答弁は、安倍さんみずからが重い時限爆弾を抱えたに等しいと考えている。
質問がどのようなものであれ、宰相の足元をすくおうとした質問にまさしく足元をすくわれるなら、すくわれた宰相の側に、最大の問題がある。
それが内閣総理大臣の責務だ。
▼特に、菅さんへの答弁に、問題がある。
村山談話と河野談話の正当性について、安倍内閣が国民に問いかける機会を、みずから失った。
なかでも平成5年に出された河野洋平官房長官(当時)の談話は、いわゆる従軍慰安婦について「日本軍の強制があった」と実質的に述べている。
河野さんは、宮沢内閣でこの官房長官を務めたあと、村山内閣などでも外相となった。そのとき、ぼくは共同通信の記者として霞クラブ(外務省記者会)にいた。
中国軍が天安門広場でパレードをし、日本の諸都市に照準を合わせている中距離弾道核ミサイル「東風21号」も行進した。そのとき「パレードに、中国の活力を感じて感動した」という趣旨の公電を外務大臣として打ったひとだ。
ぼくは強く抗議したが、ほかの記者はなぜか無関心だった。
河野洋平さんはそのあとも、小渕、森の両内閣で外相を務め、いまでは三権の長たる衆院議長閣下である。
安倍さん個人が、この談話の言う「軍による強制」は根拠がないと考えていることは、これまでの国会などでの発言から明らかだ。
平成9年5月に安倍晋三代議士は、国会で「河野談話の前提がかなり崩れてきている」と発言しているし、首相としても10月5日木曜の国会答弁で「(軍による)狭義の強制性があったかどうかの確証について、いろいろな疑問点があるのではないかと申し上げた」と述べている。
それにもかかわらず宰相としての安倍さんが、この河野談話も認めたのは、「とにかく日本政府がいったん決めた談話なんだから」ということを唯一の論拠としている。
しかし、ちょっと待ってほしい。
河野談話から4年後の平成9年3月に、参院予算委員会で平林博・内閣外政審議室長(当時)が「日本政府の調査で見つけた資料のなかに、軍による強制連行があったという証拠は一切、なかった」という趣旨で答弁した。
すなわち、日本政府はすでに河野談話を修正している。
慰安婦という、女性の尊厳をひどく損なう現実があったことは、談話の通りに認め、それが日本軍の強制によって起きたという部分は、少なくとも日本政府が集め得た資料のなかでは根拠がないとして、修正したのだ。
外政審議室長が参院予算委という公的な場でこう答弁したのは、その意味である。
だから安倍内閣が「一貫性をもって続いている日本政府が、とにかくいったん決めた談話だから」と河野談話を認めるのは、まったく論拠にならない。
それどころか、おおきな誤りのある談話が出た4年後に、せっかく日本政府が修正したことを無視して、あえて誤った時代に逆戻りしたことになる。
河野談話が出された当時の関係者のなかで、重要な人物であったひとりに、石原信雄・内閣副官房長官(当時。現在は、地方自治研究機構の理事長)がいる。
このひととぼくは、記者時代から今に至るまで、信頼関係がある。
その石原さんは、新聞や月刊誌のインタビューに、繰り返し「政府もずいぶんと探したんですけどね、強制連行を裏付けるものはなかったですね。慰安婦を募集した文書から、担当者の証言に至るまで、強制にあたるものはなかったんです」という趣旨で証言している。
これは国会答弁のような公的発言ではないから、政府が修正したことにはならないが、ぼくは石原さんが良心をかけて、あえて証言を残したと考えている。
石原さんは、公平に、「韓国で十六人の元慰安婦に聞き取り調査をしたところ、明らかに本人の意志に反して連れていかれた例があるのは否定できないと調査担当官から報告は受けた」という趣旨も述べている。
そのうえで石原さんは「日本政府がどう探しても証拠はないが、韓国の当事者は強制があったと証言し、食い違いは埋まらない。そこで、強制性を認めれば、韓国政府の意にも沿い、問題は収まるという宮沢喜一首相や河野洋平官房長官の判断があって、河野談話になった」という趣旨を語っている。
見かけよりずっと度胸の据わった石原さんらしく、率直にほんとうの経緯を語ったのだ。
▼これを書いているうちに午前零時をまわって、10月8日の日曜になった。
安倍さんはきょう、中国を訪れ、9日には韓国を訪れる。
この訪中と訪韓を実現するために、安倍さんは「安倍家康」と呼びたくなるような、したたかな動きを見せた。
それは、成果である。
しかし、おそらくはその成果を守るために、直前の衆院予算委で、なんら認める必要のない河野談話を拙速に認めてしまったのは、間違っている。
安倍さんはたぶん、訪中と訪韓で、いわゆる歴史問題で激論になると「大失敗」としてマスメディアで喧伝されることを心配したのだろう。
しかし戦後の日本のあり方を見直すならば、「揉めれば外交失敗、揉めないで相手がニコニコすれば外交成功」という、まさしく根幹から間違った外交観をただすことに、少なくとも一歩は踏み出してほしい。
具体的なことをひとつ言えば、靖国神社への参拝がある。
小泉さんは、任期中の靖国参拝を貫くなかで終始、「こころの問題だ」と言ってきた。
しかし政権の終盤には、「中国や韓国との関係において、こういう時期も必要だったと、いずれ分かる」とも述べるようになった。
後者の言葉は、きわめて正しいと考えている。
小泉さんは『中国や韓国に対しても、いわゆる歴史問題があっても、ノーと言うべきはノーと言う、すなわち内政干渉には断固、ノーと言わねばならない』という姿勢を、靖国参拝を通じて、明示した。
だから小泉さんは、「ただただ、こころの問題だ」と言ってきた自分の言葉を、最後にはいわばみずから裏切って、本音に置き換えたのだ。
『こころの問題でもあるよ。しかし、いちばん大切なのは、ノーと言うべき時にノーと言える日本になったことを、人口が世界最大の隣国にも、きちんと知らしめるために、わたしは靖国に参拝し続けたのだ』という本音が、政権の末期に露出したのだと考えている。
小泉政治には、賛否両論がある。
というより、小泉政治はそれが終わると、あっという間に否定論が力を増している気配がある。
そのなかで『小泉語』への世の評価の高さは、安倍さんの言葉が簡潔ではないだけに、変わらない。
しかし、ぼくは『小泉語』を評価できない。
お相撲の土俵の上のような場所では、「感動した」というフレーズが確かに天才的なきらめきを放っていた。
だが肝心の国政の場では、年金の保険料を払っていない時期があったのではないかという疑問に対して「人生いろいろ、会社もいろいろ」と、国会論議を愚弄する言葉で誤魔化してしまった。
その影響は、ふつうに考えられているより大きいと思う。
宰相のいい加減な発言がまかり通ったために、年金をめぐる国会審議から、真摯なところが失われた。
だから、国民の誰もが納得できない年金改革を「100年は持つ改革」とする露骨な嘘がそのまま、今のところまかり通っている。
だから靖国参拝を「こころの問題」とだけ言い続ける小泉語にも、賛同できなかった。
しかし鮮やかな引き際で権力の座からみずから降りるとき、小泉さんは、『靖国参拝は、こころの問題だけじゃない。まさしく政治と外交の問題なのだ』と国民にようやく告げたのだと、ぼくは考えている。
小泉政権が終わりに近づいたときから、マスメディアには「アジア外交の懸念」なる奇怪な言葉が溢れた。
その言葉に押されるように、硬派を標榜しているはずの評論家も、靖国参拝を支持するかどうかについて、なにやら曖昧な言葉を語るようになった。
ぼくは靖国参拝をどこまでも断固、支持する。
日本の視点だけで言っているのではない。
アジア国際社会にフェアネス(公正さ)を確立するために、必要な感覚なのだ。
中国がこれからどれほど膨張し、日本だけではない、アジア諸国に影響力を行使しようとしても、内政干渉だけは許さない。
それを日本が示さねば、アジアのどの国が示すことができるのか。
マレーシア、シンガポール、ベトナム、タイ、ぼくの知るアジアの国の多くは、中国の膨張主義に怖れを抱いている。
その怖れが、より深刻な現実とならないように、アジアで唯一、中国に対抗できる大国の日本が、内政干渉をあくまでも排する姿勢を、いま明示しておかねばならない。
小泉さんの言う、「こういう時期が必要だ」という思想には、日本の戦後を終わらせる意味があると思う。
そして、それだけではない。
アジアのこれからを考えると、今この時期にこそ、日本がきちんとアジアの国際社会に、内政にはいかなる大国も干渉できないし、いかなる歴史があろうと内政には干渉できないという独立国家自決のルールをつくっておかねばならない。
安倍さんの訪中、訪韓では、おそらく靖国参拝について明確な議論は何もないだろう。
そして中国も韓国も間違いなく、訪中と訪韓によって安倍新首相は実質的に「任期中は参拝せず」と約束したのだと、アピールする。
訪問直前の衆院予算委で、安倍さんが河野談話まで認めてしまったために、中国も韓国も「安倍は、小泉と違って、膝を屈することのある宰相だ」と解釈しているだろうからだ。
だから安倍さんは、任期中に必ず靖国神社に参拝しなければならない。
そして、内閣総理大臣であるから、24時間365日の行動が国民にみえていなければならない。すなわち「参拝したとも、しなかったとも言わない」という戦術は、もはや使えない。
もしも参拝しなかったら、この衆院予算委で村山談話や河野談話を認めたことが、中国や韓国のプレッシャーに負け、訪中と訪韓をとにかくニコニコと終わらせたいという間違った外交観に基づいていたと、みずから証明することになる。
なにより、靖国参拝がただの小泉さんの個人的な奇行のごとくになってしまい、内政干渉をあくまでも排するというほんとうの意味を、喪わせ、日本の国民益と、国益、そしてアジア社会の利益に反することになる。
それで安倍内閣が延命できるとは、ぼくはゆめ、思わない。
だから、あえて申せば、時限爆弾を抱えたのである。
その爆弾の信管を外すのは、宰相みずからがやるしかない。
安倍さんは、衆院予算委員会ですべてを間違ったのではない。
岡田克也さんが「A級戦犯を犯罪人と認めよ」と、菅さんや真紀子さんと同じように執拗に迫ったのに対して、今度は「A級戦犯と言われたようなひとを、裁く国内法がないのに、どうして犯罪人と言えるか」と、はねつけた。
しごく正当な答弁だ。
安倍さんは、もともと靖国神社は例大祭こそ大切、という考えだったから、来年10月の秋の例大祭に参拝するつもりでいると思う。
それを、あくまでも実行してほしい。
宰相になったのは、宰相であり続けるためではない。この祖国の国民と、アジア、世界のために、しなければならないことを成すためだ。
もちろん靖国参拝だけが仕事では、まさか、ない。
ほんらいは靖国神社は、わたしたち国民の生活や運命を左右するようなものではない。
それに、靖国神社そのものの現在のあり方は、ぼくは良いとは思っていない。
たとえば遊就館を若いひとが見て、なぜ祖国が戦争に負けたのか、その原因が分かるだろうか。まるで勝ったかのような展示になっている。
一例を申せば、零式戦闘機を展示しているのは、よい。だがゼロ戦は、戦争の初期にこそ大活躍したが、後期には、アメリカ軍にその弱点を見抜かれて多くが撃墜され、優秀なパイロットを大量に失うことによって、むしろ戦局を悪化させた。
帝国海軍の内部から、改良の上申書も出されたが、海軍軍令部は無視した。
そこには、現代日本にもそのまま通じる、日本型組織の根本的な弱点が居座っている。技術力は世界最高だが、自由な内部議論がきわめて乏しく、指導部に志がなく、おのれの目前の保身だけがある。
こうした敗因を、しっかりと身を抉って展示しなければならないと思う。
しかし、その靖国神社を、大問題に仕立てあげたのは、中国である。
中国が日本の頭を抑えて、アジアに覇権を立てるために戦術的に作り出した問題なのだ。
靖国神社にA級戦犯が合祀されたから、中韓と紛糾したのではない。
いわゆるA級戦犯が合祀され、さらにその事実が明らかになったあと、大平正芳首相が3回、鈴木善幸首相が実に8回、参拝しても中国も韓国もまったく無関心だった。
突如として問題にしたのは、中曽根康弘首相が「公式参拝」を掲げて参拝してからであり、その中曽根さんが、中韓の抗議で参拝をやめてから、中国と韓国は靖国参拝をまるでリトマス試験紙のように使って日本の内政に巧みに干渉するアンフェアな外交ツールに仕立てあげた。
ナショナリズムから言っているのではない。
国際法からして、アンフェアだから言っている。
外交では、こうした策略を無視して良いときもあるが、受けて立たねばならないときもある。
靖国は、もはや明らかに後者である。
参拝をここで中断すれば、日本は、戦後の歪みをさらに固着する。
初の戦後生まれの宰相、安倍さんは、参拝を続けることによって靖国が外国による内政干渉のカードであることを、やめさせなければならない。
もし安倍さんの時代に、やめさせることができなくとも、継続することによって次の首相に手渡さねばならない。
そして、みずから抱えてしまった時限爆弾の信管を外すには、それだけでは足りない。
かつて鈍牛とからかわれた大平正芳首相は、そのからかいには意を介さず、一方でみずからの職務を、十字架を背負いて歩むがごとしと呟いていたという。
ねがわくば、この祖国の新しい宰相に、より重き十字架を背負う覚悟のあらんことを。
※写真は、この2週間の過密日程出張のなかで黒部ダム(富山県)を訪れたとき、公務関係者専用の行程をいく途中に、携帯電話のカメラで撮りました。
黒部ダムは、日本が敗戦後の電力不足に苦しんでいたとき、水力発電の電源をそなえて国を復興させようと、立山連峰の想像を絶する急峻な山々を克服して造られました。
実に、171人もの工事従事者が、亡くなったのです。
平和な時代の工事で、まるで祖国防衛戦争のように闘って、目のくらむ谷底に転落死したり、発破で吹き飛ばされたり、地中トンネルの崩落に埋まるなどして、ただひとつの命を落としたひとびとが、こんなにいました。
写真に後ろ姿が写っている、こんなひとたちのなかから171人、亡くなったのです。
仕事とは、職務とは、何だろう。
山中や地中の長い行程を登りつめて、黒部ダムに至り、深いエメラルド色の黒部湖のそばにある、171人全員の名を刻んだ慰霊碑に、祈りと感謝を捧げました。
そしてダムの巨大な壁から噴き出す、真っ白な怒濤の放流を見ているとき、ぼくの胸にわっと「おまえよ、もっと捧げよ、もっと命を、捧げよ、職務に」という声にならない叫びが沸きあがりました。
黒部ダムには、かつて記者時代にも、まったく同じ行程で訪れています。
しかし、今回のような胸の叫びは沸きあがりませんでした。
今のぼくの仕事から来た、叫びなのかも知れません。
黒部行きには、独立総合研究所から研究員と総務部員のうち3人が、ぼくに同行していました。
そのことも、無意識に影響していたのかも知れません。
そのようなことを想いつつ、遠く首都でおこなわれている国会論戦をも、思いました。
まだ衆院予算委の質疑に入るまえ、代表質問の段階でしたが、なぜこの国の民主主義の根幹をなすはずの国会での論戦が、こうも不毛なのだろうか、と。
政治家たちは、ただこの国のために死んだ171人の魂に顔向けできるのだろうか。
仕事とは、職務とは、何だろうと、その意味からもふと、考えたのです。
この2週間の日々については、項をあらためて、書き込みます。
- 2014-12-31 19:29:41
- さらば
- 2014-12-30 23:57:22
- あらためて祖国へ
- 2014-12-30 17:37:16
- 簡潔にお答えしておきます
- 2014-12-26 12:00:17
- みなさん、一気の情報です。(サイン会福岡の曜日を訂正しました)
- 2014-12-26 06:46:31
- きょう欧州出張へ出発なのですが…
- 2014-12-23 22:08:28
- 知らせてくれ、というリクエストが多いので…
- 2014-12-23 12:45:01
- 実はぼくも今、知ったのですが…