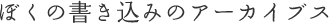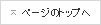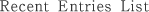2006-12-31 20:47:37
おおみそか

▼きょう大晦日は、ひさしぶりに自宅の書斎で原稿を書いている。
ことしは出張がさらに増えて、一日に飛行機に四回乗るのも、もはや当たり前に近いから、自宅にいることはかなり珍しい。
自宅も、書斎という名の仕事場にいるばかりで、たとえばリビングにいる時間がない。
夜明けまえに、たまにリビングの窓際に一分か二分ほど立ち、東京・湾岸の夜景の名残りをみる。それだけで、机に戻る。
この大晦日は、すこしだけ違う。
さきほどジムに行って、バーベルやダンベルを挙げ、フリーとブレストを泳いだ。
そこから、テレビ局に行くこともなく、海外出張に向かうこともなく、ふたたび自宅に帰ってきて、リビングから滴るような夕陽と赤い富士を、ゆっくり眺めてから書斎に戻り、原稿を書き続けている。
▼大晦日から正月にかけて、世界は同時に動きをいくらか止める。天変地異や事故それに事件は、この頃なぜか年末年始に多い。それでも、政治と外交は動きを一瞬、止める。
そのときに原稿を一気に書かないと、もう一年間ずっと原稿を書く時間はつくれない。本は出せない。
それが、この過ぎゆく二〇〇六年によく分かった。骨身に染みた。
だから、とにかくこの大晦日から正月にかけて、ひたすら書く。
そう、こころに決めている。
ぼくは、ひとりの物書きだ。
そのことを見失ってしまったら、ぼくがぼくでなくなる。
二〇〇六年も、そのまえの二〇〇五年も、いくつもの出版社から「本を出したい」というオファーがあり、それを自分の意志で受けたのに、ただの一冊も出せなかった。
途中まで書いた原稿は、たくさんある。それをプロの端くれとして完成度を高めて、着地させる、すなわち完成させる時間がとれなかった。
といっても、きょう大晦日はまだ、本の原稿には取りかかっていない。
まずは、会員制レポート『東京コンフィデンシャル・レポート』の『年始特集』の原稿を書き込んでいる。
このごろ驚くほどに増えた会員のかたがたが、配信を待っていてくれる、その熱意を間近に感じる。
だから、そのレポートを何本か書き終えてからでないと、本の執筆に入るわけにはいかない。
年始特集の配信は、一月四日に始まる。
▼ぼくにとっての二〇〇六年は、もしも一言でいうなら、苦しかった。
その一言に尽きてしまう。
不肖ながら社長・兼・首席研究員を務めているシンクタンクの独立総合研究所は、ことしも、研究本部の研究員たちや、総務部の社員たちの、献身という言葉がまさしくふさわしい清い努力で、しっかりとした貢献を地域社会と祖国に果たしたと思う。
謙遜じゃなく、社長のぼくがとてもできないような努力を、みんなが重ねてくれた。
政府機関や自治体から委託された、テロと危機から国民を護るための研究、あるいは企業から委託されたリスク管理や広報改革の研究、いずれの仕事も、研究員と総務部員のおかげで充実していた。
独立総合研究所は、どこからの支援、補助も一切、受けない。ひも付きでない。
「だから三か月ともたずに潰れる。まず人件費が払えなくなるから」と、既成シンクタンクの幹部から言われたこともある。
いやいや、黒字を続けつつ、創立五周年が近づいている。
それから、たとえば今年四月にスタートした関西テレビの新しい報道番組「ANCHOR」では、水曜日にささやかなぼくのコーナーが誕生し、その水曜日は、まずまず視聴率もよかった。
ぼくには関西テレビとなんの利害関係も、契約関係もない。
だけれど、いつしか「ANCHOR」のスタッフのなかに『青山チーム』が育ち、その誠実な仕事ぶりのスタッフのために、今年の成果はうれしかった。
だけども、それでも、正直におのれのことだけを語るならば、ぼくは今年、たいへんに苦しかった。
世間から、あるいは周りから、どう見えていようとも、ぼく自身は、そうだった。
なぜだろう。
たとえばテレビ番組については、今すぐすべての出演をやめたいと、誰にも言えない叫びを胸の奥で何度も聞いた。
一切の最終責任は、ぼく自身にある。
ただ、日本社会に深く根づいている権威主義、それと巧妙な『権力と反権力の癒着』に、苦しい思いを、内心では重ねることになった。
それは、ふだんいちばん身近にいる独研の若き秘書室長にも、言えなかった。
官僚であった時代もなく、大学の先生でもなく、もちろん国会議員でもない。
それでいて評論家という肩書きは、あくまでも、お断りしている。
もちろんタレントではない。
テレビに顔を出す人のうち実に多くの人、え、この人が、と視聴者が知ったなら思うだろう人でも世話になっている、すなわち属している芸能プロ、興行会社には一切、関わりをもたない。
そして「ヒモ付きでないシンクタンク」、つまり旧財閥や銀行、大証券会社の裏打ちがなく、権威主義からすると、あってはならないシンクタンク、その社長という立場でいる男。
そんな男は、たとえば日本のマスメディアからすれば奇妙なだけの存在であり、ほんらい、この日本では発言権がない。
▼胸のうちで、わずかに救いを感じる時は、あった。
マスメディアでいえば、硫黄島を訪ねて映画とは違う真実に触れ、それを関西テレビ「ANCHOR」で伝えようとしたときに、ぼくの力不足があっても、その真実そのものは、しっかりと視聴者が受け止めてくれた。
硫黄島に行くまえ、鳥取県米子の近郊で、新たに拉致被害者と認定された松本京子さんのお母さんとお兄さんにお会いしたときも、やはり関テレ「ANCHOR」を通じて、視聴者、国民が真正面から受け止めてくれた。
それから、意外にも官のなかで、ぼくのちいさな志、独立総合研究所の掲げる旗、理念を、おどろくほど正確に、フェアに理解するひとびとが現れている。
それでも、この国の権威主義の壁は厚い。
権力と反権力の癒着も、眼には見えないだけに、手のつけようがないほどに分厚い。
マスメディア、官僚機構、そこにだけあるのじゃない。たとえば権威主義は、決して少なくはないひとびとの意識に、無意識といえるほどに根深く、息づいている。
▼そのなかで二〇〇七年、何をするか。
まずは、書くべき原稿を書く。
それっきゃ、ない。
残りの命を、非力なりに、公に捧げ尽くして、死す。
それだけは、もはや迷いがない。
ぼくの世代は、大学紛争も高校紛争も先輩世代で終わってしまい、何もなかった世代だ。
そのためか、ぼくは学生時代、迷いに迷った。キャンパスにいながら、今すぐ学生という立場を去って、牧場で働くべきではないかと迷った。牧場の仕事になんの興味もないのに、それだからこそ、そこで働くべきではないかと迷った。
たまたま記者となって、世の中の「事実」と自然にぶつかって、次第に迷いがなくなっていった。
あまりに、つたない歩みではあるけれど(…謙遜ではありませぬ)、その歩みがあって、命を何に捧げるか、その思いが定まったことは、確かだ。
それは抽象的な、適当な話ではなく、具体的な仕事として、定まっている。
ならば原点の仕事をしっかり、やんなきゃ。
─────────────────────────────────────
*だから、自宅で机に向かっている、最近になかった大晦日は、悪くありません。
みなさん、この地味なホームページに一年間よくアクセスしてくださり、ほんとうにありがとうございました。
こころから、良いお年をと、願います。
写真は、硫黄島からの帰り、小型ジェット機から撮った、夕陽の雲海です。
ぼくの人生を変えた島からの帰り、それにどこかふさわしい、凄まじい光景でした。
- 2014-12-31 19:29:41
- さらば
- 2014-12-30 23:57:22
- あらためて祖国へ
- 2014-12-30 17:37:16
- 簡潔にお答えしておきます
- 2014-12-26 12:00:17
- みなさん、一気の情報です。(サイン会福岡の曜日を訂正しました)
- 2014-12-26 06:46:31
- きょう欧州出張へ出発なのですが…
- 2014-12-23 22:08:28
- 知らせてくれ、というリクエストが多いので…
- 2014-12-23 12:45:01
- 実はぼくも今、知ったのですが…