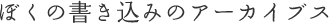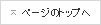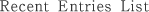2007-04-03 02:51:52
いのちの、ともしびの、影が、あわく、ふかく、ゆれる
どんなに重い責任を背負っていても、それを果たしているただ中にあっても、ひとは、ふと死に近づくことがあると思う。
中学と高校の同級生だった友がかつて、自死した。
高校一年の頃だったか、いっしょに8ミリ映画を創った。
ぼくの作は、おそらく地上最低の失敗作だった。
そして彼の作は、シナリオでは意味のない無言劇なのに、映像にしてみると、世界の底がまるごと描かれているようだった。びっくりした。映像と画像の天才がここにいると思った。
フランスの性格俳優、ジャン・ポール・ベルモンドに顔が似ていて、高校生なのにもう恋人が部屋に泊まりに来ていた。それにも、びっくりした。
彼はまずは絵描きになることを選び、東京芸術大学の油絵科に、予備校に通わずありのままの才能だけで一発で受かった。四浪、五浪もあたりまえという当時の芸大の油絵科が現役合格の新入生を迎えるのは、何十年ぶりということだった。
誰も予想しない合格を、彼もぼくも、誇りに思い、喜んだ。
彼は一回目の個展は、早くに開いた。
二回目の個展は、案内状も出し終えて開く直前に突然、みずから中止し、そのまま絵を描かなくなった。
宝石のデザイナーをしながら、おそらくは二十年ほども苦しみ続けて、いや苦しみに毅然と耐え続けて、そして、ふと、最愛のひとびとを残して、高いところから飛び降り、顔の骨を折って、逝った。
ぼくは、弁護士になっている級友と、ふたり、焼き場で、骨を拾わせてもらった。
喉の骨はあったようにも思ったが、絵描きの指の骨は、みつからなかった。
彼が、責任を放棄したと言えば、それは、たしかに、放棄した。
だけれども、ぼくはいま思う。
彼と、死なないで仕事をそれなりにしているぼくらと、その違いは、ほんとうは紙一重じゃないだろうか。
死のそばに近づく、その時は、あっけなく、なんの前触れもなく、訪れる。
そこから生の世界に戻るかどうかは、ただの紙一枚の、薄紙一枚の、違いなのだろう。
もしも戻らなくても、誰の、せいでもない。
友よ、みんな、ひとりぼっちなのだろうか。
死せる友よ、生ける友よ、ぼくらはみんなひとりぼっちか。
うん、ひとりぼっちと見切ったほうが、仕事をしやすいぞ。わたくしごころなく、いられるから。
おまえよ、水のない河を渡れ。
乾ききった石ころばかりが、ごろりごろり果てなくつづく白い河を、永遠にひとりきりで、渡ってゆけ。
中学と高校の同級生だった友がかつて、自死した。
高校一年の頃だったか、いっしょに8ミリ映画を創った。
ぼくの作は、おそらく地上最低の失敗作だった。
そして彼の作は、シナリオでは意味のない無言劇なのに、映像にしてみると、世界の底がまるごと描かれているようだった。びっくりした。映像と画像の天才がここにいると思った。
フランスの性格俳優、ジャン・ポール・ベルモンドに顔が似ていて、高校生なのにもう恋人が部屋に泊まりに来ていた。それにも、びっくりした。
彼はまずは絵描きになることを選び、東京芸術大学の油絵科に、予備校に通わずありのままの才能だけで一発で受かった。四浪、五浪もあたりまえという当時の芸大の油絵科が現役合格の新入生を迎えるのは、何十年ぶりということだった。
誰も予想しない合格を、彼もぼくも、誇りに思い、喜んだ。
彼は一回目の個展は、早くに開いた。
二回目の個展は、案内状も出し終えて開く直前に突然、みずから中止し、そのまま絵を描かなくなった。
宝石のデザイナーをしながら、おそらくは二十年ほども苦しみ続けて、いや苦しみに毅然と耐え続けて、そして、ふと、最愛のひとびとを残して、高いところから飛び降り、顔の骨を折って、逝った。
ぼくは、弁護士になっている級友と、ふたり、焼き場で、骨を拾わせてもらった。
喉の骨はあったようにも思ったが、絵描きの指の骨は、みつからなかった。
彼が、責任を放棄したと言えば、それは、たしかに、放棄した。
だけれども、ぼくはいま思う。
彼と、死なないで仕事をそれなりにしているぼくらと、その違いは、ほんとうは紙一重じゃないだろうか。
死のそばに近づく、その時は、あっけなく、なんの前触れもなく、訪れる。
そこから生の世界に戻るかどうかは、ただの紙一枚の、薄紙一枚の、違いなのだろう。
もしも戻らなくても、誰の、せいでもない。
友よ、みんな、ひとりぼっちなのだろうか。
死せる友よ、生ける友よ、ぼくらはみんなひとりぼっちか。
うん、ひとりぼっちと見切ったほうが、仕事をしやすいぞ。わたくしごころなく、いられるから。
おまえよ、水のない河を渡れ。
乾ききった石ころばかりが、ごろりごろり果てなくつづく白い河を、永遠にひとりきりで、渡ってゆけ。
- 2014-12-31 19:29:41
- さらば
- 2014-12-30 23:57:22
- あらためて祖国へ
- 2014-12-30 17:37:16
- 簡潔にお答えしておきます
- 2014-12-26 12:00:17
- みなさん、一気の情報です。(サイン会福岡の曜日を訂正しました)
- 2014-12-26 06:46:31
- きょう欧州出張へ出発なのですが…
- 2014-12-23 22:08:28
- 知らせてくれ、というリクエストが多いので…
- 2014-12-23 12:45:01
- 実はぼくも今、知ったのですが…