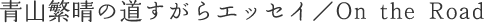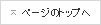2021-11-21 11:24:08
この日時は本エントリーを書き始めた時間です
この日時は本エントリーを書き始めた時間です
Comments (0)
ひとつ、書き残していました

お~い、ウエムラ。
自由になったお前は、こんな空の上もふつうに眺めているのか。
これは俺の出張中に見た空だよ。武漢熱のさなか、ルールと制限を守って乗った機中からの光景だ。植村昌樹なら、どんな絵にしたかな。
▼ひとつ前のエントリーで、「誰にもひとことも言わなかった」と記しました。
その通り、今でも親友の、良心的な弁護士となった菊井豊くんとか、日本中から患者のやって来る歯科医となった河田克之くんとかには何も言わなかった。
▼しかし、天才画家だった植村昌樹くんには、彼の自宅で、高校3年生のときに「こころのなかでコペルニクス的転回が起きた」と話したことがあります。
植村くんは、ふんと、鼻でわらっただけでした。
ぼくも、それ以上なにも話しませんでした。
彼は、その後、東京藝術大学の油絵科に、40数年ぶりという現役での合格を果たしました。
しかも、藝大の合格に必須とも言われる、藝大教授陣とのコネ、いや教えてもらうことを含めたご縁は一切無く、いきなり合格したのです。
ところが入学してから、絵をめぐる藝大の教育方針は間違っていると真っ向、逆らい、週刊誌のグラビアを破って絵に貼り付けたりする実験も行っていました。
藝大に近い上野の下宿に遊びに行くと、壁は、手を当てると隣の部屋へとベコンと凹むベニヤ板でした。
生家は、自宅にエレベーターのある素封家だったのに、清潔な男は、こんな下宿に平然と住んでいました。
そこには、入試のときに描いた自画像の油絵が置いてあり、その出来に、18歳のぼくは息を呑みました。
今でも、忘れられません。
画法は伝統的だったのです。しかし、18歳の内面を抉り出して余すところなく、そのまま歴史に残っていい絵だとすら思いました。
植村は、天才であるがゆえに、この伝統技法で描いたみずからの絵を超えようと、藝大の名声に甘え漬かること無く、懸命に苦闘していたのでしょう。
▼植村は、ぼくが記者になってから「何やってんねん。早く作家になれ」と不満をぶつけてきながら、記者としての赴任地にはるばる訪ねてきてくれたりしました。
しかしぼくは、上述の抽象的で何も分かるはずのないひとこと以外に、この植村にも、「ぼくらは自分自身を安全圏に置いて、世になにかを言っているのではないか」といったことは、なにも言いませんでした。
大学へ行きたくて行けなかったひとからすれば、この植村も、恵まれた環境に見えたでしょう。
よけいなことで、純な植村をまさか、苦しめる気はさらさらなかったのです。
▼そして、植村もぼくらもまだごく若かったとき、菊井弁護士から、当時、ぼくのいた三菱総合研究所に「おい、植村が死んだぞ」と電話がありました。
その電話では、死因については何も語られず、葬儀に参列してから、自決であることを耳打ちされました。
同級生で、葬儀の最後の最後まで残ったのは、菊井とぼくのふたりでした。
植村の額に、傷がはっきりと見えました。どんな傷かは申しませぬ。
植村昌樹、この男はぼくらすべての友だちのなかで、永遠に若く生きています。
※ 冒頭の菊井、河田両氏は、もちろん植村の友だちでもあります。
▽菊井くんは、彼の弁護士事務所の会報に最近、ぼくと息子さんの弁護士との長い対談が掲載されました。「菊井法律事務所」にもしも問い合わせていただくと分けてくれるでしょう。事務所のかっこいいサイトはここです。
▽河田君は、ぼくとの共著もあります。「青山繁晴、反逆の名医と『日本の歯』を問う ~歯みがきしても歯を失う! ~ 」です。
ワニプラスの発刊で、たとえばここです。