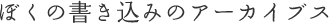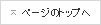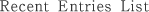2006-03-06 05:40:51
死ぬこと、生きること

寒いと聞いていた庄内平野は、東京よりむしろ穏やかに、春の気配を湛えていた。
その広い平野の一隅でひらかれた「山形県国民保護セミナー」で、ささやかな講演を終えた。
そのあと県庁や市役所、そして地域の消防団で国民保護の実務を担うひとびととの悩みを聞いて、ぼくなりに力を尽くして答える無償の会合も終えて、夕刻に、庄内空港へ向かった。
その車窓から、遠く、小さなゲレンデが見えた。きららに光るナイター照明に浮かびあがっている。
思わず、目を凝らす。
滑りたいなぁ、そう胸のなかで呟きながら。
講演会場へ着いたころには白く輝いていた、月山(がっさん)は、もう青い薄闇のなかに沈み込んでいた。
大学生のとき、初秋から冬、春、そして初夏まで、早朝から夜に至るまでアルペン・スキーで斜面を駆けおりることばかりに集中していた時期があった。
朝は、まだリフトが動き出すまえにスキーを担ぎ、ため息が出るほど登りにくい競技用スキー靴で2時間近く登り、2、3分で滑り降りてしまうこともある。
それが一日の滑りの、一本目だ。
夜は、もうナイターのリフトも止まってしまう直前に、最後のリフトに飛び乗って、スキーヤーがいなくなった無人のゲレンデの頂上に立ち、呼吸と心を整えてから、凍った雪面を思いきり滑り降りる。
それが、一日の仕上げだ。
そして真夏は、月山に、融けない雪渓を求めてやってくる。
雪渓は、スプーンカットと呼ばれる状態になっている。氷の表面をスプーンで一面にえぐっていったように、深くはないけど浅くもない凸凹ができている。
雪というより、黒ずんだ固い別物だ。
がたがたと激しく振動するスキーの振動を懸命に脚力で抑えながら、滑り降りていくと、下の方は雪渓が融けて水になっている。
間違ってそこへ突っ込むと、もはや水上スキー、止めようにも止まらない。
その先には、ごつごつと岩場が待っている。
スキーを止められないままジャンプしてしまうと、ちょっとコミカルな光景なのに、岩の上に落ちて大怪我、という笑いごとではない悲劇も起こる。
そこまで練習しても、雪国生まれでないぼくは、ちっとも、うまくならなかった。ちっとも。
だけど、あのころ自然に鍛えた足腰が、いまのぼくの体力を根っこから、支えている。
その体力に任せて、まいにち、無理に無理を重ねているけど、あのころのスキー練習と同じように、さっぱり成果は出ていない気もする。
独研、独立総合研究所は、無借金のまま黒字に転換し、日本で初めての一切ひも付きじゃないシンクタンクとして、充分に成り立っている。
成り立っているけど、いったい何をしているのか、ほとんど理解されていない気もする。
知る人ぞ知るで、政府機関、自治体、企業から、改革に関するさまざまな研究プロジェクトを順調に委託されているから、成り立っている。
だけども、一つの組織、株式会社として成り立つのが、ぼくらの最終目的じゃない。
ぼくらの祖国と世界をよくすることに、ささやかながら寄与するのが目的だから、理解が広がらないことは、やはり、すこし、つらい。
ぼくは、独研の掲げるたいまつを、次の世代、いまの若き秘書室長や、主任研究員や、研究員や、専門研究員や、ワシントン駐在員らに渡して、バトンタッチして、ひとりの物書きに戻る。いや初めて、ただの物書きになりたい。
それが、いまの夢だ。
だけど、理解をもっと広げられないと、若い世代にはまだ渡せない。
若いということは、まだ力が不充分だということでもあるから。
渡せるようになるまで、この身体が、果たして持つのかなぁと、このごろの深い、あまりに深い疲労を、身体のいちばん奥に感じて、思う。
独研が果たそうとしている任務、それが何かを海外のひとびとは、わりあいにすっと、理解してくれる。
アメリカ、ヨーロッパ、アジアの諸国、そして中東でも、文化や宗教、あるいは立場の違いを超えて、理解してくれる。
そのうえで、激しく議論もし、別れ際にこころから共感の握手を交わす。
でもね、遠慮しないで正直に言えば、日本では、なかなかそうはいかない。
かつてペルーの首都リマで共同通信・政治部の記者としてテロ事件、すなわち日本大使公邸人質事件を取材していたときオープン・カフェで、外信部のリマ支局長と、ときどき話した。
通り抜けるラテンの風が気持ちよかった。
極限の緊張に満ちたテロ取材のなかに、そういう小さな奇跡のような時間もあった。
支局長は、「あおやまさん、わたしは日本人って、意地悪だと思うんですよ。意地悪こそが、キーワードですよ、ニッポン人はね。だから、中南米がこんなにいい加減な国でもね、ここにいると、ほっとします」と繰り返し話していた。
それをときどき、折に触れて、思い出す。
だけど、ぼくは、この祖国を愛している。
仮に意地悪が満ちていても、愛している。
講演で回っていると、最初はうつむいて、背を曲げて座っていた高齢のかたが、いつのまにか背筋を伸ばし、真っ直ぐにぼくを見て、その眼がほんとうに輝きはじめることがある。
最初は、なんだか眼がきょろきょろと落ち着かない感じもあった若いひとが、すっきりと真正面から、ぼくを見つめるようになることがある。
なぜ、そうなるのか、ぼくには、はっきりとは分からない。
ただ、胸にあらためて浮かぶ言葉がある。
そうか、命がこのまま果ててもいいよね。
広くは理解されにくいなぁ、なんて、言ってる場合じゃないよ。
おまえよ、このまま尽くして尽くして尽くして、死ね。
声にならない声が、ぼくのなかでそう響いて、首をあげずに頭をあげずに、こころのなかで天を仰ぎみる。
かみさま、あなたはすべてをご存じです。
命は、隅々まで、あなたに預けます。どうぞ、意のままになさってください。
命のつきるまで、なにも願わず、無償の、無意の力を尽くし切る、残りの人生でありたいのです。
(写真は、控え室を出て、「山形県国民保護セミナー」で講演をしているときです。かけがえのない人生の時を割いて来てくださった聴衆のかたがたのなかを回りながら、なんとまぁ、強靱なはずの足と腰がふらついていました。生まれて初めて、かも。
だけど、聴衆のかたがたには、分からなかったはずです。
講演に同行して、この写真を撮ってくれた、独研の若き秘書室長、ニューヨーク育ちの大和撫子は、その事実にちゃんと気づいていました、見抜いていました。
さすが。)
- 2014-12-31 19:29:41
- さらば
- 2014-12-30 23:57:22
- あらためて祖国へ
- 2014-12-30 17:37:16
- 簡潔にお答えしておきます
- 2014-12-26 12:00:17
- みなさん、一気の情報です。(サイン会福岡の曜日を訂正しました)
- 2014-12-26 06:46:31
- きょう欧州出張へ出発なのですが…
- 2014-12-23 22:08:28
- 知らせてくれ、というリクエストが多いので…
- 2014-12-23 12:45:01
- 実はぼくも今、知ったのですが…